地域共育に関わる多様な取り組みを
インタビュー形式で紹介します。
‘風の人’の教員と地域との持続可能な関わりに必要なこと
下川町では、2020年度に「地域共育ビジョン」(*1)が策定されました。学校だけでなく、地域全体で子どもたちを育む、旗印になっています。
中でも、日々子どもたちと接する時間が長いのは保護者や先生。毎日取り組む授業や学内の活動で、手いっぱいの先生も少なくありません。(*2)また、一定年数の勤務を経て、他の地域へ異動するのが教職の常。一つの地域に長く関わり続けるのがむずかしく、町全体のビジョンや思いを理解する余裕がないまま別の学校へ転勤するケースも。
ビジョンを絵に描いた餅にせず、実現するためには、先生たちの協力と納得感が必要不可欠です。
共育ビジョンを自分ごとと受け止め、学校と地域が相互にコミュニケーションを取り、またその関係性が細く長く続くために、何が必要なのか。地域学校協働コーディネーター・本間莉恵が、下川町の小中学校で教鞭をとる鈴木靖典先生にお話を伺います。
(*1)子どもを育む地域のあり方を、様々な立場の住民15人で構成された委員会が取りまとめたもの。参考:下川町地域共育ビジョンが策定されました | 総務企画課 | 各課のページ
登場する人
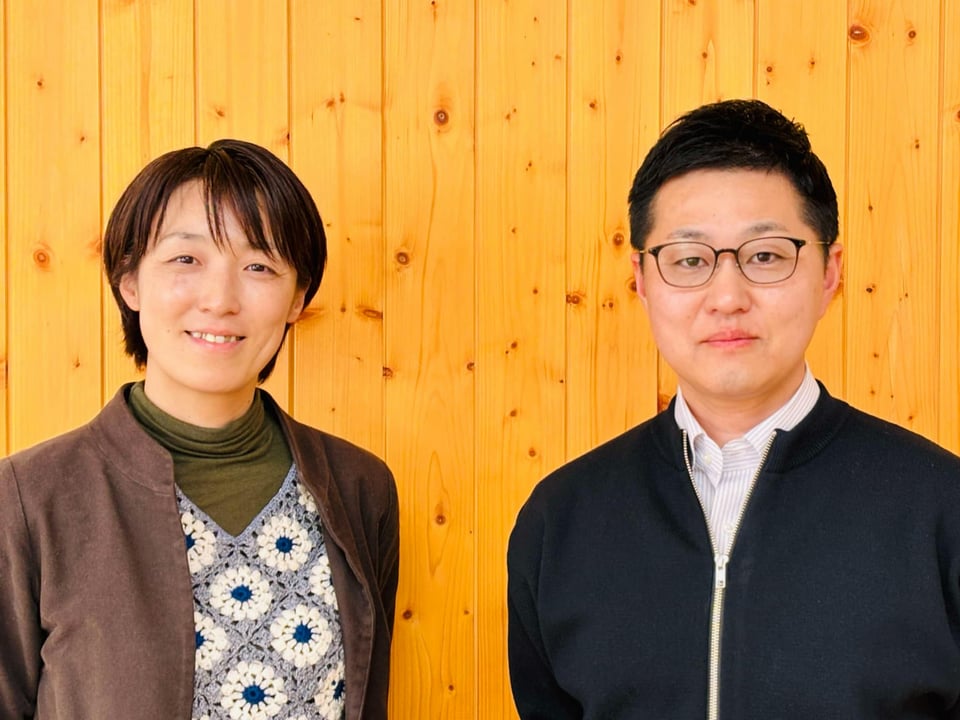
- 下川町 地域学校協働コーディネーター
- 本間莉恵 2019年8月に下川町の地域おこし協力隊に着任。2021年1月より教育委員会で地域学校協働コーディネーターを務める。
- 下川中学校 教諭
- 鈴木靖典 旭川出身。下川中学校の教務主任で、勤務5年目。町の小中一貫校の構想のもと、小中学校で数学や算数を教えている。
「この人たちは誰だろう」から始まった
── 鈴木先生は、もう下川町にはなくてはならない存在ですが──。
鈴木先生: いやいや、そんなことはないです。
── 下川町に赴任された、当初の印象を伺いたいです。
鈴木先生: 私は赴任してすぐ、総合的な学習の時間(以下、総合)の担当を任されました。4月に着任して3週間後には学習計画書を出さなければいけなくて。
右も左も分からない状態でしたが、下川中学校の総合を担当されていた先生に「本間さんやNPO法人森の生活さんがいるから大丈夫」と言われました。でも、当時は戸惑いましたね。「本間さんて、誰だろう。その’大丈夫’という確信は、どこから来るんだろう」と。

── そうですよね(笑)。
鈴木先生: 総合の授業は、地域のことを知らないと作れないと思います。でも、下川に来て間もない私に何ができるのか、困っていたところに、本間さんがすぐ声をかけてくださって。町内のいろんな方をつないだり紹介してくださったりしたんです。
私自身、自分が責任を持ってやらなければという意識もあり「助かるな」と思う一方「どこまで助けてもらっていいのか」という戸惑いもありました。
── 地域共育ビジョンを、赴任した先生方に共有する機会があったと思いますが、ビジョンに関してはどう感じられましたか?
鈴木先生: 正直、しっかり理解できたと感じるまでには1年くらいかかりました。すでに学校内でやるべきことがたくさんある先生たちにとっては「地域共育ビジョンというものがあって……」と一方的に示されると、プレッシャーに感じる可能性もあると思います。ただ、今まで赴任した地域では、「地域でこういう子どもたちを育てたいんだ」と具体的なメッセージをもらう機会がなかったため、衝撃を受けました。
── 地域と学校が関わることが、あまりなかったのでしょうか。
鈴木先生: そうですね。学校教育は学校内で完結するものという認識が、当たり前だったんです。学校側に、地域の方々を受け入れる余裕がないのか、学校への敷居の高さを感じて地域の方々が入って来づらかったのか、理由は分かりません。
鈴木先生: でも下川町に来てからは、すでに本間さんが中学校に週に1回出勤されていたり、森の生活のスタッフの方から「この授業、こんなふうにやってみるのはいかがでしょう」と提案をいただいたり、積極的に関わってくださる方の多さと、それが自然に行われていることに驚きました。町が子どもたちを支えようとしている熱量や、本来学校にだけ委ねられていた部分を、一緒に背負ってくれる存在がいる心強さを感じました。
だから私も町のことをもっと知りたいと思うようになりましたね。地域共育ビジョンについても、自分から学びにいかなきゃと感じました。

モチベーション維持、どうしてる?

── 先生方の中でも、地域との関わりに対してモチベーションや認識の差異があると思いますが、その点はどう感じられますか。
鈴木先生: おっしゃる通り、全員が同じような熱量を持つのはむずかしいなと感じます。時には本間さんや地域の方に任せきりになってしまうこともあると思うんです。でも私としては、本間さんたちが身を乗り出して関わってくれるような状態に、こちら(教員)が持っていかなきゃいけないと思います。私たちが一生懸命やらない限り、本間さんに限らず地域の方々はどう手助けしたらいいか分からないと思いますし。
── たしかに私も、何をやるにせよ先生たちが自分ごとであってほしいと思っています。こちらが提案したことだけに取り組んでいると、先生たちの負担になってしまうので。
鈴木先生: 一方、日々の業務に忙殺されている教員がいるのも現実です。ただ本間さんは、こちらの状況も理解して向き合ってくれるので、やりやすいですし他の町で実現不可能なことが可能になるんだろうなと思います。
── 先生たちが耳を傾けてくれやすいタイミングは、見極めるように気をつけています。何かの作業中に、いきなり「ピンポーン」とチャイムを押して来訪されると、手を止めて対応しなければなりませんよね。そういうコミュニケーションは取らないようにしているというか。先生たちにとって、どの「ピンポーン」が適切なタイミングなのかは、ずっと学校の外にいたらなかなか分かりません。だから、週に1回学校に出勤するときや日々のコミュニケーションで、良い間を探っている感じです。


鈴木先生: 本間さんは、私たちの凝り固まった考えをほぐしてくれる存在なんですよ。総合は、中学1年生なら50時間、中学2、3年生なら70時間もあります。これを担当教員だけで一から作るのは現実的ではありません。例えば中学校2年生の職場体験。多くの学校では、前年度を踏襲して単元作りをしていると思います。でも、下川は違う。本間さんが学校と地域の間に入り、生徒一人ひとりにじっくり向き合いながら、体験事業所(職種)が選択されていくんです。
鈴木先生: 前年度の中学1年生の総合では「25歳の自分はどんな自分だろう」というイメージを膨らませます。だから、中学1年生が2年生に上がる時点で、どの子にどんな体験を提供したら良さそうか目処が立っているんです。 それは、コーディネーターである本間さんが、前年度やこれまでの人のつながりを引き継いでくれているから。もう材料はすでに切って準備してあって、私たちはあと茹でたり炒めたりすれば完成する状態になっているわけです。

学外にもセーフティネットがある安心感
── 総合の学習を通じて、子どもたちや先生方には、どんな変化があると思いますか?
鈴木先生: 私は下川に赴任して4年しか経ってないので、子どもたちの未来にどう影響しているか判断がむずかしいですが、日常会話のちょっとした発言から、主体性を持つ子が増えてきたように感じます。
学校の授業だと、子どもたちも’やらされている’感覚が拭いきれない部分もあると思いますが、本間さんが窓口になって様々な機会を提供してくださることで、自分でバンドを始めたり、お祭りに関わりたいと言い出したりする子が出てきました。
鈴木先生: ぜんぶ、学校外の活動ではありますが、自分で情報を集めて飛び込んでいこうという動きは、なかなか起こるものではないと思います。学校という殻から外に飛び出した先で、ワクワクすることがあるのは地域がセーフティネットになっているからかもしれないですね。
── 私自身、地域のいろいろな情報提供はしていますが、いろんな企画を主催しすぎているのかなと感じることもあります。お膳立てしすぎているというか……。
鈴木先生: でも教員側からすると、ただ前年踏襲をするのではなく子どもたち側の視点に立って、中身を一緒に考えてもらえるのですごく助かると思います。


鈴木先生: それに、下川町から異動された方が他の地域で同じような総合の授業を組み立てようと思っても、全然できないと話していました。教員だけが高いモチベーション持っていてもダメだし、本間さんのようなパイプ役がいるかどうか、地域もそのパイプ役と連携しようと積極的になれるかどうか。ぜんぶが揃わないと、なかなか実現しないです。
教員は数年経ったら次の町へ移る風の人、地域の人は地に足をつけて暮らす土の人という表現があります。私たちは風の人ですから、本間さんのようなコーディネーターの存在があるからこそ、地域と切り離されずに関わり続けられると思います。
── 学校と地域の間も必要ですが、学校の中を俯瞰できる鈴木先生のような存在が、学校側のコーディネーターとして本当に重要なんだと思います。
鈴木先生: そうなんですかね。ただ、地域側の情報や声については、自分しか知らない状況は作らないようにしています。先生同士でもしっかり情報共有することが、子どもたちのためにもなりますから。いろいろな立場で子どもたちを見守ってくれる地域だと知ることは、教員側の刺激や安心感にも繋がりますからね。


